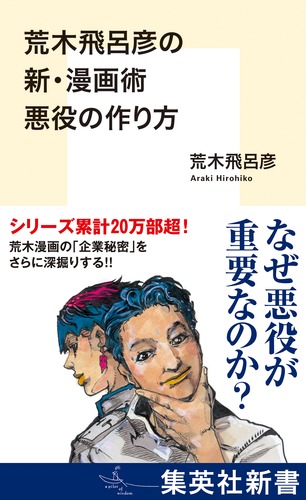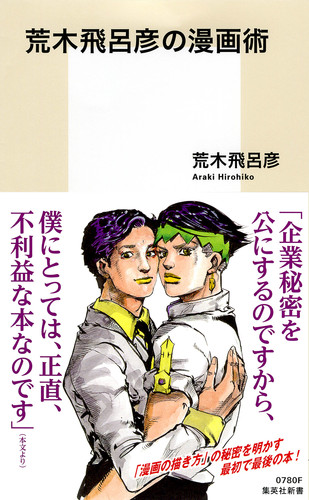本当は読みながらメモを取っていきたいのだが電子書籍だとそこがちょっと難しいのとか、あとそもそもいつも本を読んでいるときは電車の中だったりするのでなかなかメモが取りづらかったりとか
なのでこうやって読みながらメモ的にページにアウトプットすることにした。なのでその1
本についての説明はたぶんいらない(タイトルのとおりである)のでさっさとメモもとい感想その他に入る
まず荒木先生は漫画の要素が4つの事象から成り立つと考えている。これは数年前に刊行された前作にあたる「荒木飛呂彦の漫画術」の頃からの考えである(一応この漫画術も読んだが結構抜けているので今年中に読み直したい)
ここで挙げられた4つの要素は「テーマ」「世界観」「ストーリー」「キャラクター」で、これを「基本四大構造」と銘打っている。ちなみに「絵」はこれらをまとめ上げる「最強のツール(原文ママ)」として扱っている(絵についても言及しているが一旦飛ばす)
ここで面白いのは、これらは対等ではないことと、その重要性の順序がわかりやすく表された図と付随するテキストで同じではないことだ
図では「テーマ」を根幹としつつ残り3つがそれらを支える構造を取っているのだが、同時に文中では重要な順に「キャラクター」「ストーリー」「世界観」「テーマ」と掲げている
矛盾しているようだが、これはおそらく「作者の考える順序」と「読者の見える順序」が違うためだと思われる。そのことについてははっきりと言及していない
荒木先生は無意識なのか、本の内部ではこの「作者としてはこう考える」と「読者にはこう見える」が自然にスイッチされる
もちろん大抵はわかりやすく主語がついているので読み間違うことはない
荒木先生の本質的な漫画の上手さや構築の巧みさはこのあたりの感覚に付随しているのではないかとも思われる
話を戻すが、作者としてはテーマを根幹に持っておかないといけない、しかし読者はキャラクターから見る、という状況がまず触れられている
そこからストーリーや世界観を組み立て、絵でまとめながら話を作る。これがまず漫画のやることだと言っている(この辺までが前作のおさらいみたいなところ
ではキャラクターについての深堀り
キャラクターのポイントは動機、何がしたい人なのかという点
これは性格ではないことに注意。かつ同時に読者の共感を引き出すものでもある
基本的に主人公であれば「正しい」ことを動機にもってくる。文中では「友情」等が挙げられている。このへんは掲載雑誌やメディアで向き不向きがあるのでそれを考える必要もある(ジャンプならいわゆる「友情・努力・勝利」みたいな)。これは読者層によって共感する事柄が違うためと思われる。上記の通りこれらは読者の共感を引き出すためのものなので、読者に合わせる必要性はある
また、正しい動機を選んでもよい面だけでなく悪い面も考える必要はある。嫉妬、怠惰、強欲など。高みを目指し努力するが、同時にライバルに嫉妬するようなそういうやつ
逆に悪い行動を取る場合も、その動機に合わせて持ってくる必要がある。例えば殺人を行う主人公でも、相手がとても悪いやつなら許されるかもしれない、というような感じ。ただこれらは本文中でも高等テクニックとも書いているため難しい様子が見て取れる(が、人気作品は総じてそういうラインを超える行動を取らせるケースが多い気がするのである種パターンもありそう
キャラクターを作る際には荒木先生は身辺調査書を作っている。これは具体的な方法なので省略
必要なものは人間を表すもの、人に興味をもたせるものを作るという工程
「どうしてこの人はこうなのか」「なぜこんな趣味があるのだろう」「こうなるってことはこの人の親はどんな人なのだろう」というような、フックになるポイントを纏める
また複数のキャラクターで並行して作ったほうがいいと荒木先生は言っている。これはチーム内や複数キャラで要素のダブりが生まれないようにするため。さらに、作成する順序は登場順ではなく重要度が高い順にするというのもポイントで、登場するのが遅くても最初から作っておかないとストーリーの伏線を張る要素として使えないと言っている
身辺調査書はあくまで輪郭、絵で言うところのデッサンなので、作品を進めていくうちに変化することは前提として持っておく。いわゆるキャラクターのアップグレードをする
具体的には「こいつはこういうシーンでこんなことしないな」とか「過去にあった事柄はもっと悲しいものにしたほうがいいな」みたいな辻褄合わせのことを指す(実際のところは身辺調査書と辻褄が合わない状態の修正だが
この辺は具体的に話を進めて行くと発生するので(それはわかる)そこは変えても問題ないし、荒木先生は編集者の意見で変更することもあるといっている
一方で、キャラクターの芯を曲げるような変更はしてはいけない
身辺調査書はその「芯」をまとめたものなので、それをブレさせてはいけない。例えば上記の例似合わせるなら「こいつはこういうシーンでこんなことをするだろうけど……」といった感じで流れに持っていくのがそれ
いわゆる「話の都合」や「キャラクターに情が湧く」とそういうことをさせてしまう。本来そのキャラクターが死ぬシーンで死なない展開にしてしまうなど
どれだけ人気や情が湧いても「このシーンでこのキャラクターはこういうことをしますよね……そして踏み込みすぎて死にます」みたいな軸はぶれてはいけない
おそらく、理想はキャラクターと状況で物事を動かし結果としてドラマチックな展開が起こること
次回ストーリー編の方をまとめる。たぶん悪役について考えるのはもうちょっと先(一応そのあたりまで読んでるが